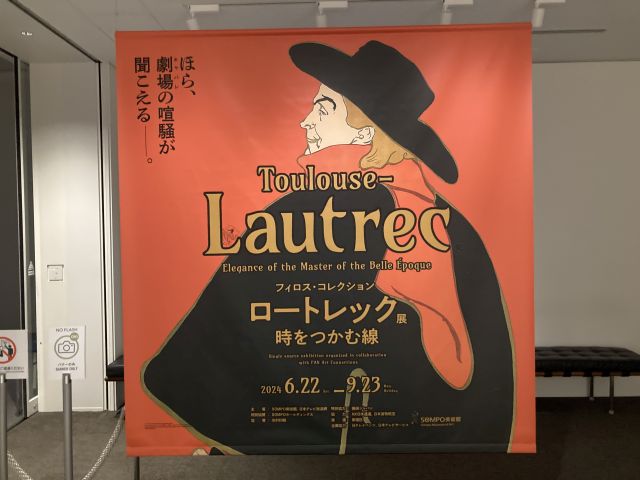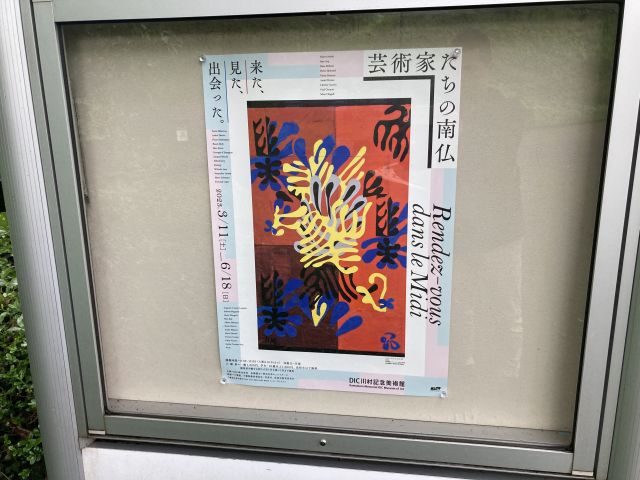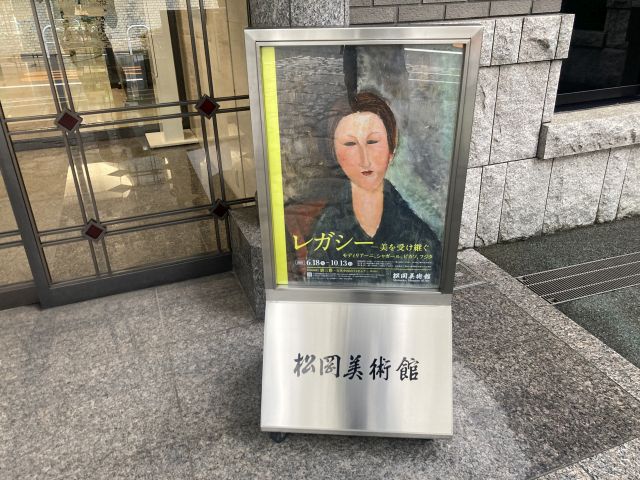鹿児島市への旅の途中、鹿児島市立美術館に立ち寄りました。
鹿児島市立美術館は、繁華街の「天文館」の近くにあります。
美術館の前にはあの有名な西郷隆盛の銅像があります。
鹿児島県の県立の美術館ではなく、鹿児島市立の美術館なんですよね。ここにモネやピカソをはじめ、素敵な作品が展示されていました。
私が訪ねた時は
冬の所蔵品展 ミニ特集:タイムスリップー100年前の美術
2022/12/13~2023/3/5
鹿児島市立美術館
作品リスト:https://www.city.kagoshima.lg.jp/artmuseum/documents/r4winter.pdf
という常設展に、ミニ特集が組まれているという展示構成でした。
見るまでは「ミニ特集」の意味がわからなかったのですが、常設展の一画に特集コーナーが組まれていました。ミニ特集の作品の一つ、マリー・ローランサンの「マンドリンのレッスン」は展覧会のホームページに紹介されていますね。鹿児島市立美術館は写真撮影不可だったので画像は紹介できないのですが、作品リストにあるヴラマンクの「花(クリスマスのバラ)」が不気味な色彩を放っていて、かなりインパクトがありました。東郷青児の「巴里の女」も怪しげでした・・・。
常設展の方は主な作品の解説カードが置かれていて、自由に持ち帰ることができるようになっています。解説カードが置いてあったのは以下の作品です。
クロード・モネ 「睡蓮」
ポール・セザンヌ 「北フランスの風景」
パブロ・ピカソ 「女の顔」
藤田嗣治 「座る女性と猫」
サルヴァドール・ダリ 「三角形の時間」
ワシリー・カンディンスキー 「二つの黒」
ルーチョ・ファンターナ 「空間概念(期待)」
ヴェナンツォ・クロチェッティ 「水浴のあと体を拭く女」
有名な画家の作品も多く、落ち着いた雰囲気でゆっくり観賞することができました。
以下、私が気になった作品です。
- ラァエル・コラン
- 令妹の像 (1879年頃)
- アルフレッド・シスレー
- サン・マメスのロワン河畔の風景 (1881年)
- ピエール=オーギュスト・ルノワール
- バラ色の服を着たコロナ・ロマノの肖像 (1912年頃)
- クロード・モネ
- 睡蓮 (1897~1898年)
- ポール・セザンヌ
- 北フランスの風景 (1897~1898年)
- オディロン・ルドン
- オフィーリア (1901~1909年頃)
- ピエール・ボナール
- 浴室の裸婦 (1914年頃)
- パブロ・ピカソ
- 女の顔 (1943年)
- ラウル・デュフィ
- ベルト・レイズの肖像 (1952年)
- ジョルジュ・ルオー
- ヴェロニカ(聖顔) (1939年)
- 藤田嗣治
- 座る女性と猫 (1923年)
- 三人姉妹 (1897~1898年)
- マルク・シャガール
- 赤い馬と太陽 (1979年)
- モイーズ・キスリング
- ブルターニュの女 (1943年)
- 赤い服の女 (1925年)
- ジュール・パスキン
- ソファに座るマルセル (1928年)
- モーリス・ユトリロ
- ブリ・シュール・マルヌの教会 (1919年頃)
- サルヴァトール・ダリ
- 三角形の時間 (1933年)
- マルク・ローランサン
- マンドリンのレッスン (1923年)
- モーリス・ド・ヴラマンク
- 花(クリスマスのバラ) (1931年)
- ワシリー・カンディンスキー
- 二つの黒 (1941年)
- 小さな世界Ⅲ (1922年)
- ルーチョ・ファンターナ
- 空間概念〈期待〉 (1961年)
- ジャン・フォートリエ
- 雲 (1960年)
- アンディ・ウォーホル
- 多色による4つのマリリン (1979-86年)
- ジム・ダイン
- 冬の9つの情景Ⅵ (1985年)
- ヴェナンツォ・クロチェッティ
- 水浴のあと体を拭く女 (1968年)
- オーギュスト・ロダン
- ユスタッシュ・ド・サン=ピエール (1889年)
- 東郷青児
- 巴里の女 (1922年)
- 黒田清輝
- 雪景 (1915年頃)
- 和田英作
- 花 (1939年)
- 海老原喜之助
- 雪の港 (1927年)